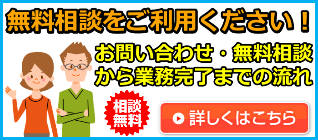子どものいないご夫婦の相続対策は、配偶者を守るためのものです。
子どものいない夫婦は、お互いを守るための対策が必要です。ご不明な点など、何なりとお問い合わせください。
子どものいないご夫婦の対策
セミナーでよくあるテーマです。
おそらく、一度は耳にした方も多いのではないでしょうか。
なぜ、子どもがいないと問題なのか?
ずばり、「配偶者を守れない」からです。
もちろん、子どもがいても、いなくても、問題は発生します。
けれど、子どものいない方の相続の場合、法律で配偶者を守らない制度になっているから問題なのです。
相続が始まった場合について具体的に考える
例えば、夫が先に亡くなり、奥様が残されたとします。その場合、相続人は、奥様と夫の兄弟となります。
受け取る相続財産は、全てが奥様となりません。法律上では、奥様が4分の3、夫のご兄弟全員で4分の1。当然、ほとんどが奥様・・・となりますので、安心される方もいるかもしれません。
ところが、平均寿命から考えると、奥様の年齢は、70代~80代。この場合、夫の兄弟姉妹も、80代~90代・・・場合によっては、兄弟姉妹の誰かが既に他界しており、その子ども(甥と姪までが相続人となります)が、相続人となる場合が多くあります。
相続人が、80歳代の奥様と、夫の兄弟姉妹や、甥姪の場合
財産はどうなるか?
よく、「財産は、ほとんどないから・・・・」と言われます。
「土地は猫のひたい程で価値はないし、家はぼろ家だからせいぜい、不動産は400万円程度かな・・預貯金は100万円あるかな?」とおっしゃる方がいたとします。
財産と言えば、すぐに大きな金額を考えがちですが、普段の視点に戻って考えると分かりますが、100万円・・・とても大きな金額です。それを、奥様と相続人全員で「分ける」事になります。
この場合、財産の総額が500万円の場合、法定相続の数字上では、奥様は価値として、500万円×4分の3=375万円となります。
法定で決まっているなら仕方ない・・・と思った方は、ここに大きな落とし穴がある事に気づいて欲しいと思います。
手続きはどうなるか・・・奥様お一人の判断では・・絶対に出来ません
奥様も含め、相続人全員の「印鑑証明書」「実印」が必要となります。さらに、遺産分割協議書などの必要書類に「署名」「捺印」が必要です。
奥様から見て、夫の兄弟・・・親しい方も居れば、疎遠な方もいるでしょう。中には、認知症や、体調が悪く、署名など出来ない方もいるかもしれません・・・(高齢ですからね・・)。もちろん、甥や姪など、何処にお住まいか??お目にかった事がない方もいるかもしれません。もしかすると、行方不明の方(実務では、たまにあります)がいるかもしれません。
ご自身に当てはめて考えると分かりやすいと思いますが、相当、大変である事は、ご理解できるのではないでしょうか。
もちろん、高齢でも健康かつ聡明な方は、大勢いらっしゃいますが、ここでは、あくまで事例として考えてください。
余談ながら、このような手続きについて、私自身は仕事としてお手伝いしています。けれど、それは奥様がお元気であったり、サポートする甥や、姪の方が居る場合です。つまり、「依頼者」がいる場合です。
もし、奥様が認知症など、何も出来ない場合、とても心配になりませんか?
不動産は、名義変更するのが大変・・・でも名義変更しなくても(お勧めする事は出来ませんが)、とりあえず、ご自宅にお住まいになる事はできます。
しかし、夫の預貯金は、解約できません。つまり、使う事ができません。
預貯金の解約には、先ほどの手続きが必ず必要となり、奥様は、ご自身以外の「相続人全員の協力をお願いする立場」となってしまいます。高齢、もしかすると、体調も悪いかもしれない・・・その場合、サポートをする身内の方は居ますか?その方も、既に高齢になっていませんか?
最悪の場合、どうなるのか・・・実はよくあるケースかもしれません。
結局、「名義変更されていない夫の不動産に住み、預貯金は解約されないまま残る」事になります。
本来であれば、夫が遺してくれた財産を、必要な介護や、お元気ならお友達との旅行などに利用できたにも関わらず、それができない事になります。これは、夫として、どう思われるでしょうか?
子どものいない夫婦の問題は、実はその後も続きます・・複雑化する相続関係
実は、これだけでは終わりません。
奥様が寿命を終えた後も続きます。夫の財産の名義変更など、相続手続きを行っていない場合、奥様が亡くなると、相続人は、「夫のご兄弟姉妹と、その甥や姪」と「奥様の兄弟姉妹と、その甥と姪」となります。
突然、自分が相続人という事でお金が入ってくるケース生まれるのは、このような場合です。
財産が沢山ある場合は、相続人が10名いても、専門家へ依頼する事で手続きができると思います。
ところが、少ない場合。奥様1人が受けるのであれば、それなりの財産であっても、相続人が何十人もいて、面倒すぎて、分ける事が断念する場合、ご主人が遺された財産は何だったんだ・・・って事になります。
もちろん、その時は、夫も妻も存在しないから関係ない・・・とは言えますが。でも、お葬式の費用は・・・・心配です。
この辺りは、「お一人様の相続」をご覧ください。
もっとも、財産については相続人の範囲が「甥、姪」まで・・なので、放置されても、最終的には国庫に入るだけ。そのため、気にしないという方もいらっしゃいますが・・
それでは、対策をどうするか?
遺言書を書け・・・というのは簡単です。問題は具体的な中身です。
お子様の居ない相続はその後、お一人様の相続へ移行します。その配慮も必要となります。
基本は遺言書。ただし、中身に注意!!
一言に遺言書と言ってもさまざまです。当然、すぐに作成できる簡単なものから、それなりのものまで順を追って説明します。なお、ここでは、説明上、書き方の詳細(法律に従って書き方)については長くなるので説明しません。記載内容として、ご覧ください。
レベル1:ないよりはあった方がいいレベルの遺言書・・それでも効果は絶大!
「私が所有する全ての財産を妻、山田花子に相続させます。」
たった、これだけですが、この1文で「相続人は妻だけ」と限定する意味がありますので、作成する価値は十分にあります。言い換えると、何十人の相続人が居ても、その手間を1文で抹消する力があるのですから!なぜなら、今回のような兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言書があれば、「遺留分」の請求を、兄弟姉妹はする事が出来ません。
遺留分のついては「遺留分の請求」をご覧ください。
ただし、自筆証書遺言の場合、相続人全員に通知したり、様々な面倒な作業が発生し、年齢的には結構、大変な作業となります。
レベル2:最低限度、これだけあればレベルの遺言書・・執行者を指定する。
レベル1に何か足りなかったのでしょうか?
遺言書でもっとも大切が記載は「執行者」です。
執行者というのは、簡単に言えば、遺言者に代わって、相続の手続きを行う人です。
執行者は、配偶者や、または友人、専門家(行政書士や司法書士)などを指定する事ができます。配偶者を指定した場合は、「執行者が代理人を選任できる」旨を追加すれば、面倒な手続きを配偶者が他の方(代理人)へ依頼する事もできます。なお、執行者を第三者にする場合、自分より若い方でなくてはなりません。また、専門家を執行者とした場合、年齢以外にも何らかの形で、連絡が取れる状況にする必要があり、自分が言うのも何ですが、あまりお勧めしません。
たとえば、こちらで、執行業務として紹介もしています。
レベル3:公正証書にする・・・安心+安全です
遺言書は公正証書にすれば、完璧・・・とは、残念ながら言うことが出来ませんが、それでも、一番のお勧めとなります。
公正証書遺言の長所や作成については、公正証書遺言の作成をご覧ください。
特に子どものいない夫婦に勧めるには理由もあります。
レベル1やレベル2を含めると・・
- 相続人を奥様に特定し、他の人に財産を渡さないですみます
- 公証人の確認作業が入りますので、相続人への連絡等を不要にし、迅速な手続きが出来ます。:詳しくは、遺言書の検認をご覧ください。
- 紛失の恐れがありません。公証役場で120歳まで(延長可能)保管されます。銀行の貸金庫など利用する必要はありません。よく金融機関で有料の保管業務を宣伝されていますが、意味がないどころか、離合集散でどうなるか分かりません。
- 特に、高齢の配偶者をサポートできる執行者についても確実に決めておく事ができますので、決める過程で、いざという時の対処を事前に考える事ができます。
遺言書と一緒に「見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言」をお勧めしています。
後見契約については「見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約」をご覧ください。
- 病気等にそなえた「見守り契約」
- 認知症など財産管理が難しくなった場合の「財産管理契約」
- 無駄な延命処置を拒否する「尊厳死宣言公正証書」
- 葬儀、入院など残債整理、諸届けを依頼する「死後事務委任契約」
- 事前のトラブル回避と相続財産でお礼ができる「公正証書遺言」
公正証書遺言でも完璧ではありません。けれど、よりよい内容にする事は出来ます
せっかく、公正証書遺言を作成しても、効果をなくす場合もあります。公正証書です?・・・そういう意味ではありません。よく、銀行で百万円もかけたから安心・・という方もいますが、何処で作成しても同じです。10万円でも100万円でも、実は全く効果は同じです。
想像力を働かせないと、所詮はマニュアル通りの遺言書でしかありません。。
つまり、大切な事は、予想する力です。
自分が亡くなった際、配偶者は、何が出来て、何が出来ないか、或いはより具体的な手続は何か・・です。これは、レベル2で指摘した「執行者」の選任も含め、大きな要因となります。
レベル2で、執行者を選任しても、その代理人の適正も考える必要があります。夫の友人の弁護士を指定された方がいましたが、残念ながら、相続が発生した時には弁護士の方は亡くなっていました。信頼は大切ですが、時間軸を考え、年齢も考慮に入れる必要があります。
不安な事を書き並べても仕方ありませんし、人それぞれの事情があります。その事情を無視して、マニュアル通りの遺言書(もちろん、多くの場合は、それでカバーできますが)を作成しても、ご自身の場合は、どうか・・・の判断は難しいものです。
よりより遺言書を作成するには、安心、安全はもちろん、将来の予想を補完する意味で、「遺言書を作成した経験」「作成した遺言書を実際に執行者として実務を行った経験」この2つの経験をご利用いただければと思います。
PCをご利用の方はお問い合わせメールフォームでお問い合わせください。
スマートフォンの方は、こちらのスマホ用お問い合わせメールフォームが便利です。SSL対応で、安全にご利用できます。