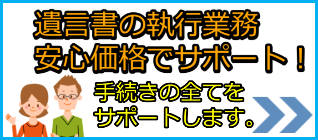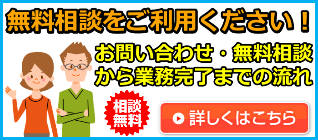
自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言は相続手続きの前に家庭裁判所の検認が必要です。八王子は立川の家庭裁判所です。
令和2年7月10日以降、自筆証書遺言保管制度をご利用の場合、「家庭裁判所の検認は不要」ととなります。詳しくは「自筆証書遺言保管制度」をご覧ください。
こちらでは保管制度を利用しなかった場合についての説明となります。
自筆証書遺言は家庭裁判所「八王子の場合は立川の家裁」の検認が必要です。
亡くなった方がご自身で作成された遺言書は、そのままでは、利用できません。家庭裁判所(八王子の場合は、立川の家庭裁判所となります)で、遺言書が、亡くなった本人によって書かれたものかどうかの確認が必要となるからです。
そのため、相続人全員への連絡、検認の際の立ち会いを依頼する流れとなります。
メニュー

自筆証書遺言を公正証書遺言にバージョンアップのチャンスです!
検認も含め、全ての相続手続きをサポートしています。
検認する前に確認する事・・法的に有効ですか?
「検認しても、実際の相続手続きにその遺言書は使えるか?」
検認の目的は「亡くなった方(被相続人)が書いたものである事の確認。」であり、家庭裁判所は「有効」「無効」の判断はしません。
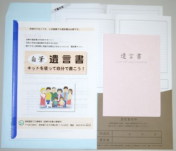
従って、検認を受けたから、法的に有効・・・とは限らないのです。
せっかく検認しても使えない・・・では、検認する意味もない事になります。
チェック方法ですが、事務所では
自筆証書遺言作成マニュアルを無料相談においでいただいた方
でご希望の方へお配りしております。
もちろん、ご自身でチェックされる場合は、市販の書籍を参考に
チェックされる事をお勧めします。
面倒な手続きをしたにもかかわらず、使えない・・では検認する
意味がありません。
検認する際に必要な書類とは・戸籍の注意点
簡単に言えば、相続人の確認が必要なので、その資料を揃える事となります。
まずは、共通な次の2点が必要となりますが、
- 被相続人の出生からの戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
相続関係によって、上記以外は変わってきます。
家庭裁判所のサイトをご紹介しましょう。
遺言書の検認・管轄裁判所
具体的には、こちらの当時者目録(PDF)をご覧ください。
ここでは、相続人の住所が必要となります。生年月日と本籍は戸籍から判明できますが、住所となれば、疎遠な方の住所を調べる事となります。
住所は「戸籍の付票」を取得する事で判明できます。これは本籍地で取得できますので、戸籍を集める際に、一緒に求めると良いと思います。
具体的な作成要領につきましては、事務所の無料相談をご利用ください。
無料ですが、必ず、満足戴ける自信があります。
検認が済んでも安心できない
無事に検認が済み、さあこれから手続きを・・・
ところで、名義変更などの手続きは「誰が」するのでしょうか?
結論から言えば、執行者が決まっていなければ、基本は「相続人全員で行う」となります。
一般の家庭であれば、対応は可能かもしれませんが、相続人が大勢いる場合は、簡単に言えば、その大勢からの「実印」と「印鑑証明書」が必要となります。特に連絡を取った事もない親戚となれば・・・むつかしくなります。
さらに、全員が「協力的」かどうかは・・・わかりません。悪気がなくとも、体調の問題などで、現実には協力出来ない場合や痴呆症などであれば、後見人など、選任が必要となる場合もあるでしょう。
未成年の方がいれば、特別代理人も必要となってきます。
検認が済んだ・・・で終わりでなく、ようやく相続手続きのスタート地点に立った・・・だけです。
そもそも、「検認という手間は必要だったのか?」と疑問になるケースも多くあります。
まずは、無料相談を利用して、手続きについての方向性、やり方を具体的に知る事が始めませんか?
遺言書の検認をご自身で行う方へのサポート
(ご自身で申請をお考えの方へ)
自筆証書遺言の場合、公正証書遺言の場合と違って、面倒な点が沢山ありますが、もちろん、ご自身で行う事も可能です。
検認手続きにおいては、相続関係を調査する事が一番のポイントとなります。
検認は、ご自身で行う予定だけれど、戸籍が集まらない・・そういった方もサポートしております。
なお、検認業務は司法書士が担当します。もちろん、お客様ご自身で、家庭裁判所への書類作成・申請も出来ます。