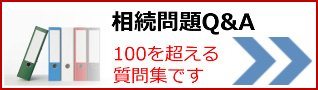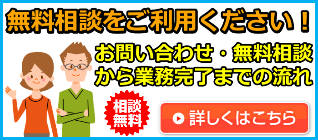
八王子で遺言書を作成して21年目。安心価格の定額です
公正証書遺言作成サポート(主に八王子公証役場で作成しています)
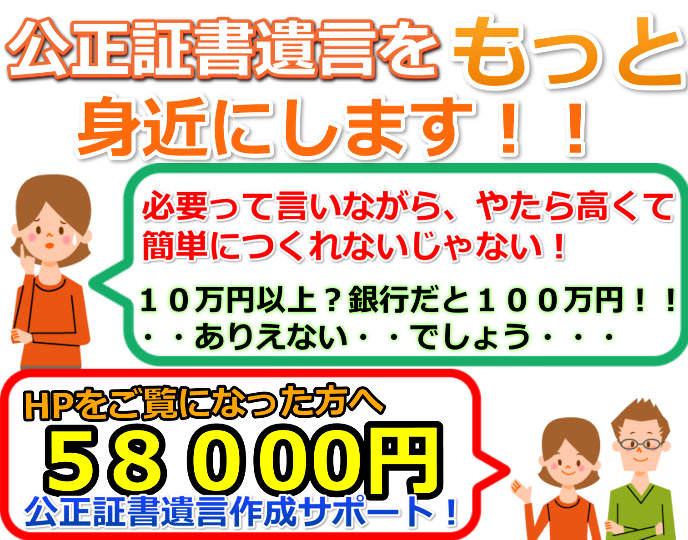
公正証書遺言作成サポート:尊厳宣言・任意後見も同時作成できます

- 遺言書作成に21年の実績から「安心・相続問題に強い遺言書」を作成します。
- 公正証書遺言が実際に使用される相続の現場を数多く見てきました。豊富な「相続の現場」経験があるから、「安心の遺言書」を作成できます。
- 価格は定額:58000円です。八王子公証役場は、事務所から徒歩1分です。
- 同時に、任意後見契約・尊厳死宣言公正証書も作成できます。
公正証書遺言と同時に作成できる任意後見契約などの役割は次の通りです。
- 病気等、特に認知症に備えた「見守り契約(任意後見契約)」
- 認知症など財産管理が難しくなった場合の「財産管理契約(任意後見契約)」
- 無駄な延命処置を拒否する「尊厳死宣言公正証書」
- 葬儀、入院など残債整理、諸届けを依頼する「死後事務委任契約(任意後見契約)」
- 大切な人を守り、事前のトラブル回避が可能な「公正証書遺言」
なお、法務局保管の自筆証書遺言との違いは、自筆証書保管制度及び弊事務所ブログ法務局保管の自筆証書遺言と公正証書遺言をご覧ください。
本当に納得できる遺言書を「定額」で作成
財産の金額で報酬がアップすることは一切ありません。「定額」です。
遺言書の基本的なご相談から始まり、納得ができる遺言書の作成までお手伝いします。
公正証書遺言作成パック 58000円
公正証書遺言を作成・・・例えば、銀行なら100万円・・ネットでしらべても、価格が不透明で、事務所で相談する前に、肝心の費用が不透明で困ってしまう事はありませんか?
実績に裏付けられた豊富な経験があるから58000円で安心できる遺言書が作成できます。 (費用一覧)ご夫婦同時作成(相互遺言)は、お二人で98000円
遺言書を作成する目的は、ご夫婦、「お互いを守る」ためではないでしょうか?
特にお子様が居ない場合など、ご夫婦で作成した遺言がなければ、夫(妻)の財産は、法的には4分の3しか受け取る事ができません。
ところが、遺言書があれば、夫(妻)の財産の全てを受け取る事ができます。しかも「遺留分」も発生しません。法的にも安心して財産を遺す事ができます。
遺言書を作成の際は、ご検討ください。お二人でこの金額ならリーゾナブルです。
見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約:48000円
将来の自分についての、「見守り」「財産管理」「死後事務」を元気な間に、公正証書で契約(任意後見契約)するものです。
遺言書と同時に作成できますので、手間と時間が省けます。
さらにくわしい内容は任意後見契約:見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約をご覧ください。
尊厳死宣言公正証書の作成:10000円
ご夫婦同時作成は、「お二人で15000円 !」
尊厳死宣言とは簡単に言えば、ご自身がお元気なうちに、延命処置を行わない事を「宣言」するものです。
公正証書遺言と同時に作成する場合、追加書類は不要です。
公正証書遺言と同時の場合、作成時間は10分程度です。
さらにくわしい内容は尊厳死宣言、延命治療の拒否をご覧ください。
公正証書遺言作成費用の詳細
| メニュー | 料金 (税別) |
詳細 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 作成パック |
¥58,000 | 1 遺言書案分作成 一番、大切な執行者の選任 を含んでいます。 2 公証役場作成の案文のご提供 (実際に作成するものと同じものです) 3 必要に応じた、改訂 4 公証役場作成日程調整 |
| 夫婦同時の 公正証書遺言 作成パック |
¥98,000 | ご夫婦一緒に公正証書遺言を作成するパックです。内容は上記の公正証書遺言作成パックと全く同じです。 ※ お二人分で「98000円」の、お得な「定額」パック |
| 公正証書遺言の 証人 |
¥10,000(1名) | ご自宅など公証役場以外で作成する場合は出張費 5,000円と交通費実費が追加。 公証役場での作成は出張費(2時間まで)は発生しません。 |
| 記載事項の追加 | ¥10,000 | 基本パックに追加する場合: 1) 不動産の追加(1筆) 2) 金融機関の追加(何行でも) 3) 葬祭承継者の選任 4) 相続人の追加(1名) 5) 二次相続の追加 <例> 遺言者が長女へ財産を相続させる遺言の場合、万が一、遺言者よりも長女が先に亡くなった場合に備え、遺言者の孫などに相続させる、または遺贈する文章を追加する場合 6) 付言事項(こちらで案分を作成します) |
| 複雑な事案の追加 | ¥30,000 | 上記に追加して、例えば葬儀の内容など、項目の追加では収まらない事案を追加する場合です。(詳細は、ご相談ください) |
| 戸籍謄本・評価証明書・名寄帳などの取得 | ¥3,500 | 公正証書遺言作成パックの方が対象です。 公証役場で必要となる書類をお客様に代わって取得するサービスです。 |
| 見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約 | ¥48,000 | 公正証書遺言と同時に作成しますので、全く手間がかかりません。 任意後見、3点セットです。 |
| 尊厳死宣言公正証書の作成 | ¥10,000 | 公正証書遺言と同時に作成しますので、全く手間がかかりません。 |
| エンディングノートの作成サポート | ¥30,000 | 公正証書遺言作成パックの方対象です。 |
| 自筆証書遺言の検認 | ¥90,000 | 家庭裁判所への手続きサポートです。司法書士による代理申請です。 |
| 相続財産調査 | ¥50,000 | 財産目録の作成 |
上記以外の費用は無料相談でご確認ください。
八王子公証役場での遺言作成の実績が豊富にあります。
まずは無料相談を利用して、お気軽にご相談ください。
遺言書作成オリジナルDVD・遺言書メニュー
公正証書遺言の作り方オリジナルDVDの紹介
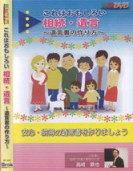
公正証書遺言の基礎から作成までを解説したDVDが発売されております。
事務所へ相談に来られた方で、ご希望の方へこのDVDをプレゼントしています。
※ 事務所オリジナル遺言書マニュアルの動画版です。
遺言書メニュー

遺言の基本的な考え方、公正証書遺言、自筆証書遺言の作成要領、一般的な費用については、遺言書の書き方をご覧ください。
どんな遺言書が作れるか?(相続対策としての活用もできます)
遺言書と一口に言っても、目的によって、内容はさまざまです。
事務所で作成する代表的な遺言書の例を紹介します。
- 配偶者の将来の生活を配慮する
- 障害など、特定の子供の将来のため
- 相続権のない者(相続人以外)へ財産を遺す
- 老妻や身障者の介護など、条件や負担をつけて特定の者へ相続させる
- 予備的遺言(配偶者など、自分と同時、または以前に先立って死亡)
- 遺産を信託財産として他人に管理させる
- 葬儀などの方法を希望する場合
- 在日外国人が遺言書を作成する場合
ご自身に当てはまりそうな遺言書はありましたでしょうか?
特に、お子様がいないご夫婦の場合、公正証書遺言書の作成は必要です。
具体的な相続事例として子どものいないご夫婦をご覧ください。なぜ、問題なのかを詳しく事例を含め、解説しています。
もちろん、上記以外にもさまざまな条件での作成や、複合した遺言書も作成しております。
遺言書には、よくある、配偶者やお子様へ「○○を相続させる」といったものから、いわゆる「相続対策」として作成するものまでです。
お気軽にご相談ください。
遺言が特に必要な方
- 子どもがいない夫婦
- ステップファミリー
- お世話になっている方がいる場合(子どもの嫁など)
- 相続人が居ないかた
- 不動産など遺産分割すると価値が低下する財産をお持ちの方
財産が多い少ないは、関係ありません。 相続が始まった方の15%が家庭裁判所に相談へ行く時代です。
遺言書は、亡くなって初めて効力が生じます。亡くなるまでは、ただの紙切れです。
しかし、「今」書かなければいけない遺言書は、将来の契約書です。大切だからこそ、公正証書にする事をお勧めしています。
遺言の必要性について次のページで確認できます。
「遺書」と「遺言書」は違います。
「遺書」は生きている間に、「言いたかった事」などの気持ちを書いたものです。
「遺言」は、これからの自分自身の財産管理について書いたものです。
一番大切な事は「ご自身の思い」を伝える。 二番目に大切な事は「財産を託された家族を配慮する。」ことです。
一番大切な事については、お客様の意志ですからご自身で決めて戴きます。
ただし、二番目については多様なご提案ができるものと思います。
遺言書の作成で一番、大切なところです。 お一人お一人にあった遺言書作成のお手伝い、アドバイスを行っています。